<他ページへリンク>
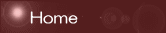 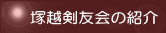 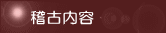  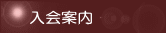     
|

− 剣道稽古 − <小学生>
|
 1.フォーミングアップ 1.フォーミングアップ |
剣道の稽古に入る前に、ランニングおよび準備体操やストレッチを行います。その後、基礎体力作りのために、腕立て伏せや腹筋なども行います。
|
 |
 |
 2.竹刀による素振り 2.竹刀による素振り |
竹刀による正しい振りを練習します。竹刀の持ち方、構え等を一人ひとりに対して指導します。素振りは正面打ち、交差面打ち、早素振り等を行います。小学生低学年の子供は、手の振りと足さばきのタイミングが合わず苦労しています。
|
 |
 |
 3.木刀による基本打ち 3.木刀による基本打ち |
木刀による正しい基本打ちを練習します。前進および後退しながら正面打ち、交差面打ち、早素振り等を行います。竹刀の素振りと違うところは、実際に元立ちの先生が持つ打ち込み棒に対して、打突部位を狙って素早い冴えのある打ちを練習します。
|
 |
 |
 4.防具を付けて基本打ち稽古 4.防具を付けて基本打ち稽古 |
面を着けないAコース(低学年および初心者)、防具を全て着けて稽古するBコース(3年生〜4年生)、Cコース(5年生〜6年生)合同で行います。初めは、基本打ち(面、小手、胴)を4本毎に元立ちの先生に打ち込んでいきます。次に、打突の機会を与えながら基本打ちを行います。(打突の機会とは、相手が打ちに出ようとするタイミング)
|
 |
 |
 5.打込み掛かり稽古、地稽古、切り返し 5.打込み掛かり稽古、地稽古、切り返し |
稽古のまとめてとして、打込み掛かり稽古(元立ちの先生が指示した打突部位を打ち込む)、地稽古(元立ちの先生と相対して打ち合う)を行う。最後に切り返し(面、左右面の複合打ち込み)を行い、一日の稽古は終了となります。
|
 |
 |
 その他まとめ その他まとめ |
稽古の前後に座礼を行います。稽古開始時は、座礼に加え大きな声を出す訓練を行います。(剣道は声が出せなければ一本は取れません。また、声を出すことで力強い冴えのある打ちが出ます。)この様に一日の稽古は、剣道の技を習得するだけではなく、礼儀を学ぶことや集中力を養うための訓練も行います。
|
 |
 |

− 剣道稽古 − <中学生から大人>
|
 1.基本稽古 1.基本稽古 |
中学生以上は、30分〜40分程度基本打ちの稽古を初めに行います。相手に対して交互に打ち込みます。メニューは以下のとおりです。
⇒ それぞれ4本を打ち込む。大きく面打ち、二足一刀の面打ち(左足を素早く引き寄せる)、一足一刀の面打ち(足を継がない)、小手面の二段打ち、胴打ち、出頭の面(相手が出ようとすることろをとらえる)、面6本に対してお互いに面の応じ技を打ち込む、出頭の小手、相小手面、小手すり上げ面、小手6本に対してお互い小手の応じ技を打ち込む。など。
⇒ 基本稽古のまとめとして、面、小手面、相面、相小手面、面で二の太刀の面をそれぞれ4本(計20本)を2セット打ち込み、最後は切り返しで締める。
|
 |
  |
 2.地稽古 2.地稽古 |
地稽古は元立ちの先生に対して、中学生から一般の大人が掛かる。時間で30分程度。
|
 |
 |
 − 居合稽古 − − 居合稽古 −
|
 稽古内容と流派について 稽古内容と流派について |
全日本剣道連盟居合(以下全剣連居合)を入門編として稽古しています。全剣連居合は居合の流派が数多くある中、各流派の基本的なものを抜き出し総合して、剣道人ならば少なくともこの程度は知っている、そして抜くことができることを目的として制定(形12本)されました。
古流の流派は夢想神伝流です。
全剣連居合の初段取得後、初伝(大森流型12本)の稽古をします。昇段するに伴い、中伝(長谷川英信流型10本)の稽古に入ります。
|
 |
  |
|